そんな中、この4月10日、名古屋市の国際デザインセンター行われた「パワートーク」は、アジア圏のデザイン事情を知る非常に貴重な機会であった。
渡部千春(デザインジャーナリスト)

「アジアという未知数」を見て
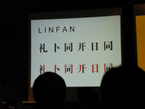


| 専門誌だけでなく一般誌にもデザインのトピックが頻繁に載るようになっているが、その情報は日本あるいは欧州、米国からのものがほとんどで、近隣であるアジア圏からのデザイン情報はなかなか入ってこない。関心はあってもそれを知る機会さえない、というのが実情である。 そんな中、この4月10日、名古屋市の国際デザインセンター行われた「パワートーク」は、アジア圏のデザイン事情を知る非常に貴重な機会であった。 |
|
|
渡部千春(デザインジャーナリスト)
|
|
 |
|
|
|
|
| イーストミーツイースト 「アジアという未知数」を見て |
|
|
|
|
| 講演者はマレーシア人建築家のヒン・タン氏、シンガポール人建築家のワン・チュー・マン氏、中国人プロダクトデザイナーのリン・ファン氏、インド人プロダクトデザイナーのマイケル・フォーリー氏、タイのプロダクトデザインチーム「プロパガンダ」の5組。それぞれ1時間づつトークを行い、最後の1時間は京都市立芸術大学教授で建築家の池上俊郎氏と名古屋市在住のプロダクトデザイナーである本田敬氏を交え、全員が会してのトークセッションを行った。7時間に及ぶプログラムだったが、すべてが新鮮で飽きさせない内容となった。 |
|
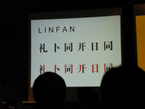 |
もちろん、アジアと一口に言ってもそれぞれの国の事情や個々のデザイナーのアプローチは異なる。例えば「中国には現代建築の上に中国様式の屋根を付けたりするようなことはもうないにしても、まだその悪影響が残っている。家電製品に関してはコピーの域を出ず、独自のモノが作られてはいない」と言うリン・ファン氏は、個人のプロジェクト作品として、筆のフォルムを用いたボールペンや、切り絵やステンドグラスをモチーフにしたいすなどを発表。伝統とコンテンポラリーの融合に画策している様子がうかがえた。 |
 |
主に時計のデザインを行っているマイケル・フォーリー氏は「インドではモアイズベター。装飾はあればあるほどいい」と言う。彼のインハウスデザイナーとしての時計や店舗のデザインはこうした消費者意識を反映してか、金の色味が強いものや鮮やかな色彩のものが多かったが、個人のプロトタイプ作品ではハイテク志向のシンプルなフォルムになっている。 |
 |
家庭用雑貨のプロデュースを行っているプロパガンダの作品には強い国民性はなく、縦置きが可能な皿や、電球そのままの形をマッチ棒の頭に見立てたランプなど、ドローグデザインなどにも通じるユーモアが見られた。 |
| アジアをテーマにしたトークだっただけに地域性や民族性が話題に上ったが、「多様な民族を抱えるマレーシアでは自国のルーツを探り出すのは難しい」というヒン・タン氏の意見は、グローバル化の先にあるものを予見している。特に輸出を前提にしたプロダクトデザインでは、世界に出ていく際に何を独自性としていくのかが問われるが、この点では日本人も含めすべての参加者が各々模索をしているように感じた。今回のような機会をステップに情報交換が密になれば、模索の先にあるものが見えてくるかもしれない。 | |