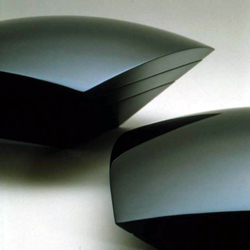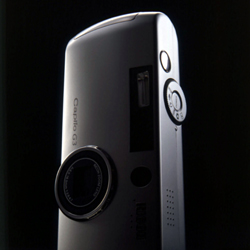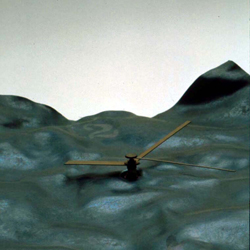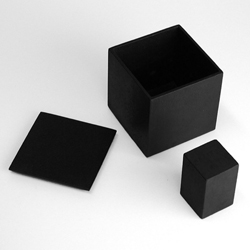|
国際デザインセンターが毎年開催する特別企画展「デザイナーズ・シリーズ」の第5回では、建築家、プロダクトデザイナーとして幅広く活躍する黒川雅之氏の個展―「陰翳」解体新書/黒川雅之の自己解剖を、6月6日から22日にわたりデザインミュージアム+デザインギャラリーを会場に開催する。
今回の展覧会は、黒川氏の作品とその思想を、「陰翳」というキーワードをもとに“解剖”していくという大変意欲的な試みとなる。このテーマに込められた意味や展覧会への抱負、また黒川氏の幅広い活動について、インタビューで語っていただいた。
|
| IdcN |
まず、今回の展覧会のテーマ「陰翳」についてお話いただけますか?
|
| 黒川 |
作品とは何だろうと考えますと、アーティストにとって作品づくりとは、自分の「告白」なんだと思ったのです。いかに生きるべきかということと、どんな仕事をするかということはイコールだと常日頃から考えています。いわば、自分の思想の全てを表現し、自分の感動をそのまま「詩」にするのが作品であると。デザイナーたるものはまず自分のために創るのが当然だと思っています。
|
|
お客はそれを見て感動し、共感を表明する形で買うわけです。買わないで通り過ぎる人は「僕の意見と君の意見は違うよ」と言っているわけで、マーケットと街とは商品を通じて、ユーザーとデザイナー、またはメーカーと議論したり会話をしている状態なんですね。カンバセーションが街=商業空間をつくるわけです。
|
|
自分の作品を外に見せるということは自分の意見を言うことなのですが、こと展覧会や出版となると、それをまとめて語ろうとすることですから、自分自身を解剖して「黒川という人間は何を考えているのか」、この人間の中にある思想をすべて腑分けするような作業に思えたのです。だから"解体新書""自己解剖"と名付けたわけで、これは真剣に自分をさらけ出す意志表示でもあります。
|
|
近頃、自分の中で去来するあるイメージ、感覚、思想というものがあるのですが、それが結果的に「陰翳」という言葉で表現されたのです。少し挑戦的に表現すると、この展覧会の目的は、自己の仕事・思想を解剖することで発見した「陰翳」の概念によって、〈依然として世界を支配する西洋的近代思想〉を告発することであり、〈日本の思想に深く沈潜する世界を救う思想〉を見つけ出すことにあると言えます。
|
|
近代思想はキリスト教的西洋思想の世界制覇のようなところがあって、さまざまな土着文化との闘争を生んできました。今その反省と見直しの動きがあると思います。だから東洋の、あるいは日本の思想が、新たな思想にシフトするきっかけになるのではないかと思います。これは自分自身が日常的な仕事を通じて見つけてきたことなのです。発見してきた概念、キーワードが、最も包括的で重要だと思われる言葉-「陰翳」に収斂してきたわけです。
|
|
この「陰翳」の背後にあるのは「負の価値」の復権であり、「豊穰なミニマリズム」であり、「重層性」や「並列性」の概念、そして価値の「相対性」などのキーワードです。こうした意味を包括する「陰翳」というテーマを、作品と16のキーワードで解析していこうと思います。
|
| IdcN |
これまでの長い創造活動の中で一貫している思想を「陰翳」という言葉に集約し、ご自分自身を客観的にとらえる試みをされるということでしょうか。
|
| 黒川 |
ある意味では客観的なんでしょうが、自己解剖というのはやはり主観的にならざるを得ないと思います。虚心坦懐に自身を見つめ直し、自己の過去の作品を読み直してみることによってさまざまなものが見えてきます。実は文章として「黒川雅之の50のデザインのキーワード」のような形でもまとめてみたいと考えているんです。ことばと作品―「キーワーズ&キーワークス」ですね。それらはお互いにオーバーラップした関係で、例えれば指圧や針の経絡のようにロジックが三次元的につながっている、それとそのつながりの発見を自分自身の「解剖学」と呼んでいるのです。
|
|
これまでの思想を整理してみて、またそこから新たな挑戦をしてみたい。また、こうした主張が近代以後の21世紀の世界をつくるためのヒントになると、確信をもって展覧会や出版をしていきたいと思います。
|
| IdcN |
具体的にはどのような作品が紹介されるのでしょうか?
|
| 黒川 |
家具や時計、デジタルカメラ、漆器、車両、スクリーン、照明器具など実にさまざまな種類のものですが、会場の雰囲気はほとんど白と黒とシルバーの「色のない世界」。光と陰はあるのですが、非色彩の素材色をイメージしています。
|
| IdcN |
いま、もっとも関心を持っていらっしゃることや今後の抱負、あるいは現在のデザインの状況についてのお考えをお聞かせ下さい。
|
| 黒川 |
自分がこうありたいと思うことが、結果的に社会にとっても意味を持つことになればいいですね。「存在で語る詩人」になりたい。モノや建築や環境など、詩をうたうように創りたいと思います。自分自身のために創造することほど真摯に創る姿勢、言い訳のきかない創り方はないし、ものの生まれる出発点はそこだと思います。今回の展覧会もすべての出発点に戻る作業といえます。それが僕の今後の抱負であるし、これからのデザインのあり方へのメッセージにもなるでしょう。
|
| IdcN |
物学研究会、デザイントープなど、幅広くネットワークを作る活動もされていますね。
|
| 黒川 |
僕自身の活動の幅広さというのは、深めるために広げているところがありますね。活動を大きく二つにわけると、一つは創作活動、つまり自分がもっとも得意とする方法で自分の世界観を表現していくことで、黒川雅之建築設計事務所あるいはK-システムの活動です。それに対してデザイントープという会社と物学研究会はコミュニティ・マネジメント、関係づくりの仕事ですね。
|
|
哲学的にいえばこの二つとも創作活動といえますし、また両方とも社会教育活動でもあります。デザイントープで行うコンペや、物学研究会のセミナーなどはもちろん、デザインの創作活動もモノを通じて人に影響を与えるわけですから教育活動です。モノを媒体として入っていくのと、人間関係を媒体として入っていく違いだけかもしれません。
|
|
創ることは生き方の形だと思っていますから、デザイントープも物学研究会も創作のひとつの形といえるでしょう。そして今回の展覧会は僕にとって大きな創作活動の節目になると思っています。
|
|
(インタビュアー:国際デザインセンター 黒田千香子 2003年3月18日 (株)黒川雅之建築設計事務所にて)
|
|
|